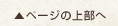韓国語中級学習者の元気の素講座
| 講座1<心がまえと音読のしかた> | 講座2<口蓋音化> | 講座3<ㅂ変則> |
| 「韓国語中級学習者のための元気の素講座」を始めます。『前田式韓国語中級文法トレーニング』(アルク)から重要ポイントを拾って、わかりやすく解説をつけ、みなさんと一緒に学んでいく講座です。毎週土曜日に更新しますので、チャンネル登録してください。テキストがなくても学習できるように工夫をしていきます。 第1回目は、<心がまえと音読のしかた>です。 | 口蓋音化とは何か? 같이 を取り上げ、わかりやすく解説しました。元気の素、その2です。 | ㅂ変則用言の活用を取り上げました。テキスト(前中)のp15です。合わせて해요体の-作り方も復習しています。 ㅂ変則は、口を閉じることを途中でやめてしまって、唇性(くちびるせい)だけが残ります。つまり、本来으となるべきところが우というように、唇が寄る音になっているわけです。これはこじつけではなく、歴史的な変遷から、確かに言えることです。 変則活用も、こうして理解できると覚えるのが楽ですね。 |
| 講座4<고 싶다> | 講座5<ㅎ変則> | 講座6<子音字母の名称> |
| 希望願望の表現は、会話などでよく使います。고 싶다は、用言の語幹にそのまま接続すればいいだけなので、簡単です。さまざまな表現を見てみましょう。そして日本語とのずれについても知っておくと便利です。 | ㅎ変則活用は、かなり特殊です。活用の仕方も特色があり、語彙も「こそあ」などと色彩語彙に偏っています。特殊なものはかえって覚えやすいです。그러면 그래요とみなさんがなじんでいる活用をモデルに、他の語彙をあてはめていきましょう。 | ㄴとかㅇとか、子音字母の名称は覚えにくいですね。でも原理原則を理解して整理すると簡単です。 |
| 講座7<クイックレスポンスのやり方> | 講座8<調音点> | 講座9<鼻音化> |
| クイックレスポンスは単語記憶術の一つです。ゲーム感覚で単語が覚えられます。自分で簡単に作ることもできます。ぜひこの方法をお試しください。 | 声のできる仕組みについて知っておくと、あとあと発音や、音変化が理解しやすくなります。まず口の構造と、調音点(ちょうおんてん)についてしっかり理解しましょう。 | 音変化の中でも、頻度が高く、しかも音印象が変わるのが鼻音化です。早い段階できちんと理解しておきましょう。調音点の一番近い鼻音に変わります。 |
| 講座10<多読> | 講座11<群読> | 講座12<ㄹ語幹用言の活用> |
| 中級学習者は、テキスト以外にもいろんなものをどんどん読んでいかなければなりません。『学習エッセイ対訳集』をお勧めします。日韓クロスバージョン音声付き【ミレ韓国語学院】http://www.emire.jp/ こちらから購入できます。 | 声のできる仕組みについて知っておくと、あとあと発音や、音変化が理解しやすくなります。まず口の構造と、調音点(ちょうおんてん)についてしっかり理解しましょう。 | 用言の種類は3つ。母音語幹用言、子音語幹用言とㄹ語幹用言です。そのうちのㄹ語幹用言の活用についてまとめました。覚え方の秘訣があるんです。 |
| 講座13<音変化のまとめ> | 講座14<ピッチパターン> | 講座15<数字の読み方> |
| 韓国語の音変化は一体いくつあるのか? 早い段階で全体像をつかんでおくと不安感がなくなります。ざっと一瞥しておきましょう。 | 韓国語のピッチパターン(音の高低)について解説しました。東京での「発音クリニック特別講座」の一部です。 | 数字の読み方は、「日付」「生年月日」「時間」など、日常生活でよく使う定番の読み方で習熟してください。カタマリで一気に言うよい練習になります。 |
| 講座16<으変則> | 講座17<르変則> | 講座18<音の高低の原則>改訂 |
| 韓国語の으変則活用について簡単にまとめました。変則活用はよく使う代表的な単語でパターンをしっかり覚えていくのが一番の近道です。 | 르変則についてまとめました。前回の으変則と対比させてしっかりと覚えてください。 | 韓国語の音の高低は、日本語母語話者にはなじみにくいところがあります。ここでは音の高低の原則をpraat(音声分析ソフト)を使って、分かりやすく説明しました。改訂版 |
| 講座19<韓国の歌> | 講座20<勧誘> | 講座21<ㄴ挿入> |
| 第3回ぷち合宿inミレ(2013年7月27日・28日)で、韓国の歌を学びました。「개똥 벌레(ほたる)」と「그녀를 만나는 곳 100미터 전(彼女に会う場所100メートル前)という2曲です。メロディーに乗せると自然に感情のこもった韓国語になります。 | 勧誘表現は자、または읍시다を付けます。簡潔に説明しました。 | ㄴ挿入は、韓国語の音変化の中でも最も理解しにくい変化です。通常音変化とは「発音しやすいように変化する」ものですが、ㄴ挿入は、日本語母語話者にとっては「発音しづらくに変化するわかりにくい音変化」という印象になりがちです。簡潔に整理してみました。※動画の中では「テキスト21ページ」と言っていますが「29ページ」の誤りです。すみません。 |
| 講座22<否定> | 講座23<ㄷ変則> | 講座24<音読練習> |
| 否定表現の作り方の基本、後置否定と前置否定について説明をしました。 | ㄷ変則活用について簡単にまとめました。正則活用との対比を通して特徴をつかんでください。 | 「中級パワーアップⅢ」の中間復習の授業で。音読をしっかり練習します。音読しつつ個々の発音を直していきます。活動量が豊富なので、みなさん力を付けてきています。 |
| 講座25<位置・方向> | 講座26<疑問詞> | 講座27<가지다と들다> |
| 位置・方向を表す単語を整理してみました。自信をもって言えるように、ペアで覚えましょう。 | 5W1Hにあたる6하원칙(6何原則)について簡潔にまとめました。疑問詞が使いこなせると会話で相手に質問ができるようになります。 | 類義語は比較して、違いをしっかり把握しましょう。ここでは「持つ」という意味の가지다と들다を取り上げました。 |
| 講座28<笑顔と泣き顔> | 講座29<二重パッチムの読み方> | 講座30<激音化> |
| 「笑顔」と「泣き顔」は紙一重? 鼻音化とㄹ語幹用言の活用と、いろいろ復習になりますよ。 | 二重パッチムのどちらを読んだらいいのか迷った時の秘訣を説明しました。 | 激音化の説明を簡潔にしてみました。まずは激音がちゃんと発音できているか確認しましょう。 |
| 講座31<ㅅ変則> | 講座32<下称体(한다体)> | 講座33<中級突破4BD&音読初回> |
| ㅅ変則について簡単にまとめました。 | 韓国語の文末の表現形式は、大きく分けて3つあります。합니다体、해요体、한다体です。今まで一番なじみの少なかった한다体ですが、新聞などで使われる文体です。作り方を簡潔に説明しました。 | 4色ボールペンディクテーションと音読の授業の実際を見てください。 |
| 講座34<ことわざ> | 講座35<受け身> | 講座36<使役> |
| 韓国語でよく使われることわざをいくつか選んで紹介しました。ことわざには、その民族の知恵が詰まっています。使用頻度の高いことわざを覚えて、使えるようにしましょう。四字熟語なども関連させて覚えましょう。 | 受け身表現はちょっと複雑です。整理すると3つの類型に分けることができます。具体的に例を挙げながら説明しました。 | 使役表現も3つの類型に分けることができます。整理するとわかりやすいです。知っている単語で表現の幅が増えます。 |
| 講座37<濃音化> | 講座38<Praatによる音読分析> | 講座39<기を使った慣用表現> |
| 音変化の中で最も複雑・多様なものが濃音化です。何のマーカーもありません。同じつづりなのに、濃音で発音する単語もあり、平音で発音する単語もあるのです。タイプ分けをしても例外も多いという、大変厄介なところです。ここでは、漢字語の接尾辞が付く場合に関して簡単にまとめてみました。 | 音声分析ソフトPraatを使って受講生の音読音声を分析してみました。音声は一瞬にして消えてなくなります。こうして録音して詳細に分析してみることも時には必要です。ミレの「発音クリニック」ではみなさんの音読をこのようにPraat分析して差し上げます。 | 기を使った慣用表現はたくさんあります。ここでは、少し発展させて、때문에(~のために)の類似表現も見てみました。 |
| 講座40<ミレオリジナル学習格言> | 講座41<줄 알다/모르다> | 講座42<群読その2> |
| 外国語の学習は長丁場です。「励みになる言葉」をいくつか韓国語で覚えておくと便利です。モチベーションの維持と、文法や音変化の定着にも役に立ちます。ミレオリジナル学習格言のクリアファイルもあります。 | 可能表現の「수 있다」「줄 알다」 の違いを説明しました。そのほか、「줄 알다 / 모르다」 の用例など、いくつか紹介しました。 | 群読その2です。上級演習講座の学期最終授業で、実施しました。題材は『韓国語上級演習ノート』(白帝社)、韓訳3「あと一匹」です。練習風景付き。 |
| 講座43<発音クリニック模擬授業> | 講座44<韓国の歌2014> | 講座45<ネーはどうしてデーに聞こえるのか> |
| 八重洲ブックセンターでの講演会(発音クリニック模擬授業)を白水社が撮影してくださいました。その一部(導入部分)を抜粋しました。画像と感想はこちらhttp://mire-k.jp/ybc.htmをご覧ください。 | 第4回ぷち合宿inミレの中から「韓国の歌」です。 | 韓国語の네(ネー、「はい」)は、日本人の耳には時にはデーのように聞こえます。それはどうしてか、簡潔に説明してみました。名古屋初級突破大作戦の中の一コマです。 |

 06-6344-8996
06-6344-8996